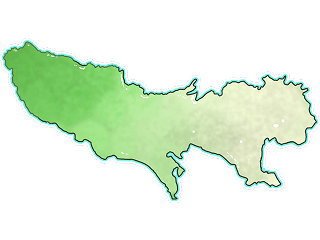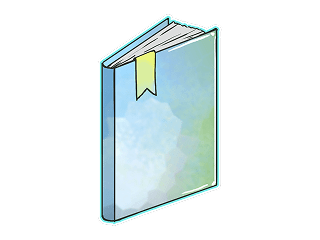草ぼうぼうの藪が懐かしい
小野展嗣

写真:草地に棲むワスレナグモのメス(体長14 mm)
幼稚園から大学まで18年間(1958〜1976年)、私は都内の学校に電車で通学した。その後、ドイツへの留学を経て1983年に自然史博物館に採用されて以来、研究員という立場で洗練されていく近代都市東京の街や自然の変化を体感してきた。とくに1964年の東京オリンピックを契機とした急激な市街化と、バブル(1989年前後)後の高層化には目を見張るものがある。
東京砂漠(都区部)にオアシスとも言える大型の緑地(皇居の庭園、明治神宮の森および白金の自然教育園)がある。それぞれ広大な敷地からおよそ200種のクモが記録されている。この数はしかし八王子市に生息するクモの種数の半分に満たない。比較的乾燥に強く移動能力が高く、餌の選り好みをせず多様な昆虫を狩り、子孫を残す能力に優れたクモは、都会の緑地でもたくましく生き残っているが、多くの種がだんだんいなくなっている。
大型の種では、ジョロウグモは毎年あちこちで見られるが、オニグモやコアシダカグモは市街地ではほとんど姿を消した。また、草むらに棲むカニグモやハエトリグモ、あるいはコモリグモのなかまなどが衰退しているように見える。
草ぼうぼうで良いのだ、と言いたいところだが、都会では天然自然より景観が優先され、草刈りが奨励される。かつてよく見かけたいわゆる藪がなくなり、ひらけた場所は芝生の広場や公園として整備されている。都会は、とくに草地性のクモが棲みにくい環境になっているような気がする。

小野展嗣 (国立科学博物館名誉研究員)
1954年生まれ。学習院大学法学部卒業、ドイツ・マインツ大学生物学部中退。理学博士(京都大学)。国立科学博物館研究主幹(九州大学客員教授兼任)を2019年に定年退職し現在名誉研究員。日本動物学会永年会員、日本蜘蛛学会名誉会員。専門分野は動物学、昆虫学、とくにクモ類。ベトナム、タイ、ミャンマーなどを踏査。国際クモ学会賞受賞(2010年)。小学館の図鑑NEO『昆虫』・『危険生物』、『節足動物の多様性と系統』(裳華房)、『日本産クモ類生態図鑑』(東海大学出版部)、『あしの多い虫図鑑』(偕成社)など著書多数。