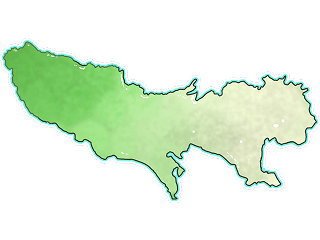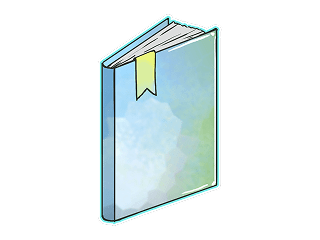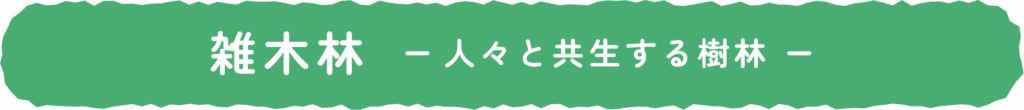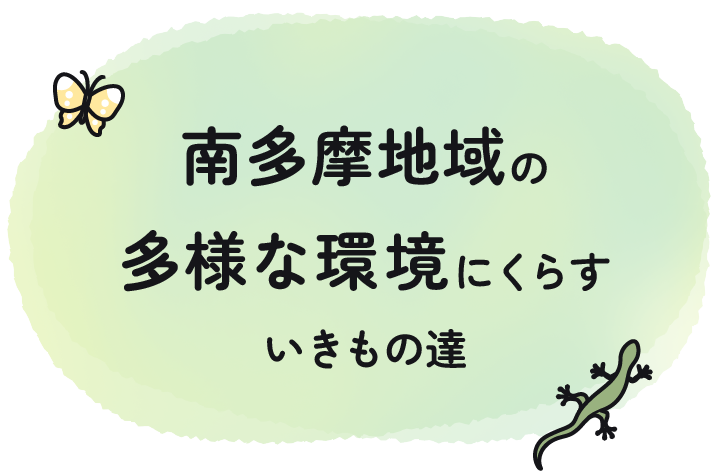


谷戸とは丘陵地が浸食されてできた、斜面林と谷に広がる低地からなる地形です。谷に湧き出る湧水を活かして稲作が行われ、「谷戸田(やとだ)」の景観が生まれました。きれいな水が常に供給されるため、水辺のいきものにとって重要なすみかになっています。

ホトケドジョウ
Photo by Cybisters
日本固有の小さなドジョウで、きれいな湧き水や小川にしか生息できません。水底の泥や枯草の下に隠れてくらしています。

シュレーゲルアオガエル
Photo by お構いなく
日本固有のカエルで、昼間は隠れて「コロロ」と鳴いています。

サワガニ
Photo by みみいかK
日本固有のカニで、水質の良さを示すいきものです。

クヌギやコナラなどの落葉樹が中心の森。薪や炭の材料、肥料になる落ち葉などを得るために人々が定期的に手入れをすることで、多様ないきものを育む豊かな環境が維持されてきました。

タマノカンアオイ
Photo by ツクツクギボウシ
関東地方南部のみに分布する常緑の多年草です。春、多摩丘陵の林の中で、落ち葉に埋もれるようにひっそりと花を咲かせます。

スミナガシ
Photo by チカトコ
墨を流したような渋い模様の翅が特徴です。

ニリンソウ
Photo by てくてくあるく
早春の雑木林で、1~4個の花を咲かせます。

ホトトギス
Photo by カシノナガキクワナイ
日本固有種で、秋の雑木林で花を咲かせます。

アカボシゴマダラ
Photo by hidzuom
中国大陸原産で、在来のチョウと食草(エノキ)をめぐって競合します。

南多摩には多摩川の支流である浅川や、町田市を源流域とする鶴見川など、川幅や流速の異なる様々な川が流れています。川沿いに連なる林や草地は、水辺のいきものにとって重要な生息地になっています。

カワラケツメイ
Photo by Mushizukioyako
8~10月頃、河原や土手などで黄色い花を咲かせます。

ウラゴマダラシジミ
Photo by simasimamoka
幼虫はイボタノキの葉を食べます。

ギバチ
Photo by Rdeer
ナマズの仲間で、砂地や水草が生えるきれいな川に生息します。

マユタテアカネ
Photo by appios
池や沼、流れの緩やかな川で見られる赤とんぼです。

ニホンカワトンボ
Photo by マチダコキクイムシ
樹林に囲まれた、比較的きれいな川の中流から上流にかけて生息するトンボです。清流のシンボルとも言える存在です。

住宅地の公園、庭木、街路樹、生垣など、私たちの暮らしのすぐそばにある緑。人工的に整備された場所も含め、こういった場所にも様々ないきものがくらしており、身近な自然観察の場となります。

ミノウスバ
Photo by お構いなく
ガの仲間で、幼虫は生垣などにもよく使われるニシキギ科の植物を食べます。

アナグマ
Photo by くろましい
タヌキとよく間違われますがイタチの仲間です。

ガビチョウ
Photo by キョウトコキクイムシ
美しい声でさえずる鳥ですが、もともと日本にはいなかった「外来種」です。分布が拡大しており、在来の鳥との競合など、生態系への影響が心配されています。
※ ここでは、東京都レッドデータブック2023の本土部のカテゴリーが純絶滅危惧NT以上のものを「希少種」としています。また、掲載されている生物の写真はすべて調査期間中にBiomeアプリに投稿されたものです。
※ 本ページの内容は、2025年に開催された特別展「多摩市の生きもの大集合!~市民が調べた多摩市の生物多様性~」に掲載内容です。