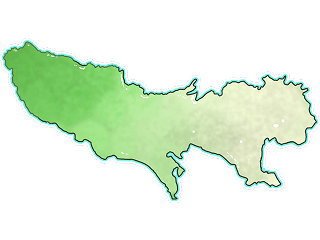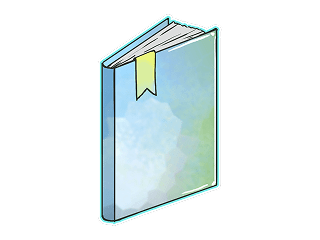秋~冬に注目の鳥たち
都市化による土地利用の変化や、地球温暖化にともなう気候の変動は、東京の鳥たちのくらしにも影響を与えています。数を減らして見かけにくくなった鳥もいれば、逆に環境の変化に適応して数が増えている鳥もいます。また、外来の鳥が新たに定着し、在来の鳥たちの生活に影響を与える事例も各地で報告されています。
こうした鳥たちの状況をできるだけリアルタイムで把握することは、地域の生態系を守っていくために重要です。
コガモ
ドバトくらいの大きさで、日本で見られるカモ類のなかで最も小柄です。オスは栗色の頭に目の後ろが光沢のある緑色、脇には白地に細かい黒い波模様というカラフルな装いで、メスは全身茶色の地味な模様をしています。カモ類の中でも早い時期に渡ってくることで知られ、公園の池や湖沼、川など様々な場所で見られます。時々逆立ちして水面下の餌をとり、水面からお尻だけ出すかわいらしい姿も見られます。

ハシビロガモ
全長43-56 cm、長いヘラ型のシャベルのようなくちばしが特徴的なカモ。オスは白、黒、緑、茶色のコントラストが鮮やかで、メスは全体的に茶色っぽい模様をしています。幅広のくちばしを水面に浮かべ、内側にあるブラシ状の突起で濾しとって食べるのが特徴で、数羽で集まって水面をくるくる回りながら採食する姿もよく見られます。池や湖などの水辺で、独特な行動と大きなくちばしに注目して探してみましょう!


キンクロハジロ
全長40-47 cm、金色の目と黒と白のツートンカラーが印象的なカモ。オスは黒と白のコントラストがはっきりしており、後頭部のまげのような冠羽が特徴です。メスは全体的に茶色っぽい色をしています。池や湖などでよく見られ、潜水して貝類などをとって食べます。群れで行動することも多く、飛び立つときには水面を走るように助走してから羽ばたく、ダイナミックな姿も観察できます。

モズ
一年を通して見られますが、秋になると「ケケケッ!キーキー!」と高鳴きし、自分の縄張りを主張することから、日本の秋を告げる鳥とされています。全長約20cmと小さな身体ながら、タカのようにカギ型の鋭い嘴と頑丈な爪を持ち、カエルや昆虫、小鳥や小型の哺乳類を捕らえる肉食性です。獲物を木の枝先などに突き刺して残す「はやにえ」の習性も、秋によく見られます。

ジョウビタキ
ジョウビタキは夏に北の地域で繁殖し、冬鳥として日本に渡ってきます。サイズはスズメと同じくらいか少し小さく、オスはオレンジのお腹に黒い顔と銀髪頭、メスは茶色の身体に翼の白い斑が特徴です。多くは10月中旬以降に渡ってきますが、早ければ10月上旬頃から姿をみせることも。「ヒタキ」の名の由来でもある火打石を打つような「ヒッ、ヒッ」という地鳴きも特徴的で、見つける手がかりになります。今シーズン初のジョウビタキを見つけるべく耳を澄ましてみましょう!

ユリカモメ
東京都の都民の鳥として親しまれるユリカモメ。カムチャツカ半島などから冬鳥として日本の海岸や河川にやってきます。全長40cmほどで、白い身体に赤い脚と嘴が特徴です。比較的大きな群れを作って生活し、優雅に泳ぐ姿や、群れで飛ぶ華やかな姿を見ることができます。北海道などには8月頃から渡来しはじめ、そこから徐々に南下し、10月下旬ごろに本州へ到着することが多いです。少し時期は早いですが、北から渡ってくる姿に出会えるかもしれません。

最新の動向をキャッチ!
ここでは、特に都内での個体数や生息域の変化を探りたい鳥たちを紹介します。もし見かけたら、ぜひ写真を撮って投稿してください。調査団員の皆さまからの投稿の一つ一つが、貴重なデータとして蓄積されます!
土地利用の変化によって減少中 ホオジロ
全長16.5㎝ほどでスズメより少し大きく、「チョッピチュ ピーチューチュチッ」などと囀ります。
かつては都内の里地や草地で普通に見られましたが、1970年代以降、減少傾向にあります。
耕作地の減少や、宅地開発などによって、ホオジロが好む草地や低木林が減少したことがその要因とされています。現在では、河川敷の草地が主な生息地になっているようです。

都市部で増加中 ハヤブサ
優れた飛翔能力や、狩りの巧みさで知られる猛禽類です。全長はメス49㎝、オス42㎝ほど。ハシボソガラスより少し小さいくらいの大きさです。山地の岩場や海岸の崖に巣を作りますが、近年では都市の高層ビルや鉄塔を「人工の崖」として利用し、繁殖する姿が観察されています。エサになるドバトがたくさんいることも、ハヤブサの都市での暮らしを支える要因となっているようです。

内陸部にも進出中 イソヒヨドリ
全長23.5~25㎝ほどで、オスは青と赤褐色の鮮やかな体色、メスは灰褐色の斑模様が特徴です。もともとは海岸の磯(いそ)に生息することから「海辺の鳥」として知られるイソヒヨドリですが、近年では東京都心、さらには八王子などの内陸部まで、分布を拡大しています。もともと岩場を好んで営巣するため、それに似たコンクリートの構造物が彼らのくらしに適しているのかもしれませんが、はっきりとした理由はわかっていません。現在進行形で生息域を拡大しているイソヒヨドリの動向について、ぜひ情報をお寄せください!


都市部で増加中 ワカケホンセイインコ
インドやパキスタン、スリランカ原産の外来種で、全長は40cmほどです。ペットとして輸入されたものが逃げ出して野生化したと考えられています。都市部はタカなどの天敵が少ないことから、公園などで繁殖し、電線や街路樹に大群でとまっている様子がよく目撃されています。木の洞(うろ)を利用して巣を作るため、同じように洞を利用する在来の鳥類と、営巣場所をめぐって競合する可能性が指摘されています。

多摩地域で増加中 ガビチョウ
中国や東南アジア原産の外来種で、全長は20~25cmほど。目のまわりの白いアイラインが特徴的な鳥です。ワカケホンセイインコと同様、ペットとして輸入されたものが逃げ出すなどして定着したと考えられています。都内では多摩地域に多く生息しており、丘陵地の森林のほか、民家のすぐ近くでも見られます。鳴きまねが得意で、ほかの鳥の声を取り入れながら、複雑でやかましいさえずりをします。