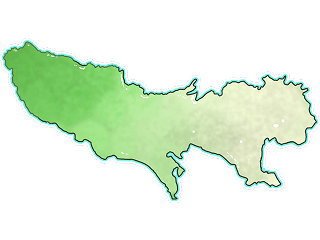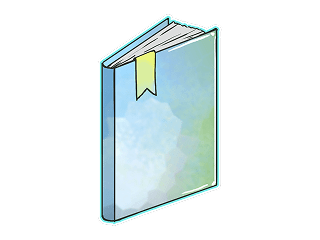秋の散策のお土産・ひっつき虫
秋が深まる季節、公園や野山でいきもの観察をしていると、いつのまにか衣服に小さな植物の種子がたくさんくっついていた、という経験はないでしょうか。少し厄介にも思えるこの「お土産」は、自力では動けない植物たちが、歳月をかけて洗練させてきた種子散布戦略の結晶です。
通称「ひっつき虫」と呼ばれるこれらの種子は、動物や私たち人間の移動を利用して分布を拡大します。こうした種子散布の様式は、「動物付着散布」と呼ばれます。
ひっつき虫がひっつく仕組み
「ひっつき虫」と一口に言っても、その付着の仕組みは様々です。先端がかぎ状に尖ることで衣服の繊維や動物の毛に食い込む「かぎ爪型」、たくさんの細かい棘がマジックテープのように機能し絡みつく「とげとげ型」、分泌される粘液によって粘着する「ネバネバ型」があります。
ルーペや顕微鏡などを使いながら、どんな仕組みでくっついているのかを、ぜひ観察してみてください。



かぎ爪でひっつく
ヌスビトハギ
日本全土の道端や林縁で見られるマメ科の植物です。秋になると熟す扁平な果実の表面にはかぎ状の毛が密生しており、これが衣服などにしっかりとくっつきます。諸説ありますが、一説では泥棒が抜き足差し足で歩いたつまさきの足跡に実が似ていることから、この名前が付きました。


オナモミ
日本全国の道端や河原などの荒れ地に生育します。硬い総苞(そうほう)に包まれた果実には、1~2mm程度の鉤状のトゲがたくさん生えており、これが動物の毛などに絡みつくことで運ばれます。


トゲトゲでひっつく
ヤナギイノコヅチ
本州(関東地方以西)、四国、九州の山地の林内に自生するヒユ科の植物です。秋になると、果実を包む苞(ほう)の先端が硬く鋭いトゲ状になり、通りかかる動物や人の衣服に突き刺さって付着します。


タウコギ
田んぼや湿地に生えるキク科の一年草です。秋に実る痩果(そうか)の先端には鋭い2本のトゲがあり、これが水鳥の羽毛や人の衣服に付着することで種子が運ばれます。かつてはごく普通に見られた植物ですが、近年では生育地の減少やアメリカセンダングサなどの外来種との競合により、地域によっては数を減らしています。


ネバネバでひっつく
メナモミ
北海道から九州の山野や道端で見られるキク科の一年草です。果実を包むヘラ状の総苞片(そうほうへん)から粘液を分泌し、その粘着力で動物などにくっつきます。オナモミ(雄ナモミ)に比べて付着する力が弱いことから、「雌ナモミ」と名付けられたと言われています。


チヂミザサ
チヂミザサは、日本全土の森林内など、やや湿った半日陰の場所に群生するイネ科の植物です。その名の通り、葉が笹に似ており、縁が縮れたように波打っているのが特徴です。秋になると、熟した果実の先端にある芒(のぎ)から粘液を出し、通りかかる動物の体に付着して種子を散布します。