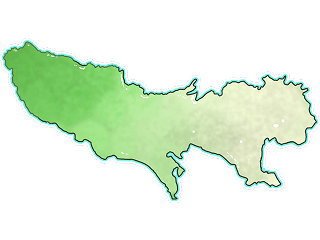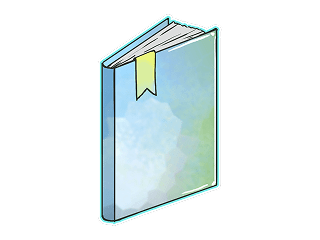花に劣らず美しい果実をつける植物たち
春や夏に花を咲かせる樹木の多くは、秋になると果実をつけます。ここでは、花に劣らず美しい果実をつける植物たちを5種紹介します。
数を減らしている種
オトコヨウゾメ
ガマズミ科ガマズミ属の落葉低木です。山地の林縁などに生育しますが、都内では生育環境の減少により数を減らしています。9から10月にかけて楕円状球形の果実をつけます。この果実は長さ8mmほどで、数個ずつ枝から垂れ下がります。葉は傷ついたり乾燥したりすると黒く変色する性質があります。

コバノガマズミ
ガマズミ科ガマズミ属の落葉低木です。
9月から11月にかけて長さ5〜7mmほどの卵球形の赤い果実をつけます。山地や丘陵地、里山の林などでみられますが、都市化や雑木林などの管理放棄が進み、生育地の環境が減っている種のひとつです。
オトコヨウゾメとよく似ており見分けるのは困難ですが、一番わかりやすいのは果実の形です。オトコヨウゾメの果実がやや長細いのに対し、コバノガマズミはより丸い形をしています。その他、下記のような違いがあるので、じっくり観察して種名を決定しましょう。
| オトコヨウゾメ | コバノガマズミ |
|---|---|
| ★果実が楕円状球形(やや長細い) | ★果実が卵球形(丸い) |
| 果実は垂れ下がるようにつく | 果実は上向きから斜上程度で垂れ下がらない |
| 葉柄の赤みが強い | ー |
| 押し葉にすると黒くなる | ー |

都内の林で見られる種
ゴンズイ
ミツバウツギ科ゴンズイ属の落葉小高木で、日当たりのよい、やや乾燥した雑木林の林縁で見られます。
9月から11月にかけて直径1cmほどの果実をつけ、熟すと赤い果実が割れて黒く光沢のある種子が顔を出します。このような相反する色の組み合わせは補色効果を生み、鳥などの散布者に見つけてもらいやすくなるといわれています。

サワフタギ
ハイノキ科ハイノキ属の落葉低木で、沢をふさぐように茂ることが名前の由来であり、山地や丘陵地の谷沿いなど湿った環境を好む植物です。
9月から11月にかけて、自然界では珍しい瑠璃色の実をつけます。しかも樹木で青い実をつける種類は多くはありません。果実は落葉後も枝についたまま残り、人間の食用には向きませんが、メジロやキビタキなど小鳥が食します。

分布を広げている種
トウネズミモチ
モクセイ科イボタノキ属の常緑小高木です。中国原産で、明治以降に日本に持ち込まれました。大気汚染に強いため、都市部での道路や公園の緑化に使用されますが、近年都市近郊の二次林などで野生化した本種が確認されています。
秋から冬にかけて熟す黒紫色の果実には、ヒヨドリをはじめとする果実食の野鳥がたくさんやってきます。
在来種のネズミモチとは葉や果実の特徴で見分けることができます。ぜひ覚えてトウネズミモチの分布を調査してみてください。
| トウネズミモチ | ネズミモチ |
|---|---|
| 果実は楕円形だがやや丸みがある | 果実は楕円形で細長い |
| 葉はネズミモチより大きく、日にかざすと葉脈が透ける | 葉は光沢があり、葉を日にが差しても葉脈が透けない |

ネズミモチの仲間には、紹介した2種のほかに、イボタノキや、それによく似た中国・ベトナム原産のコミノネズミモチなどがあります。これらは葉の先が丸いので、トウネズミモチやネズミモチと区別できます。

島しょ部で見られる種
モモタマナ
シクンシ科モモタマナ属の半落葉性の高木です。大きなものでは高さ25mにもなります。
日本では琉球列島と小笠原諸島に分布します。果実は水に浮き、海流によって散布されるので、海岸に生えているのがよく見られます。
果実は長さ3-6cmの大きな堅い果実です(頭上から落ちてくると痛いです)。果実の皮は、オガサワラオオコウモリの好物です。